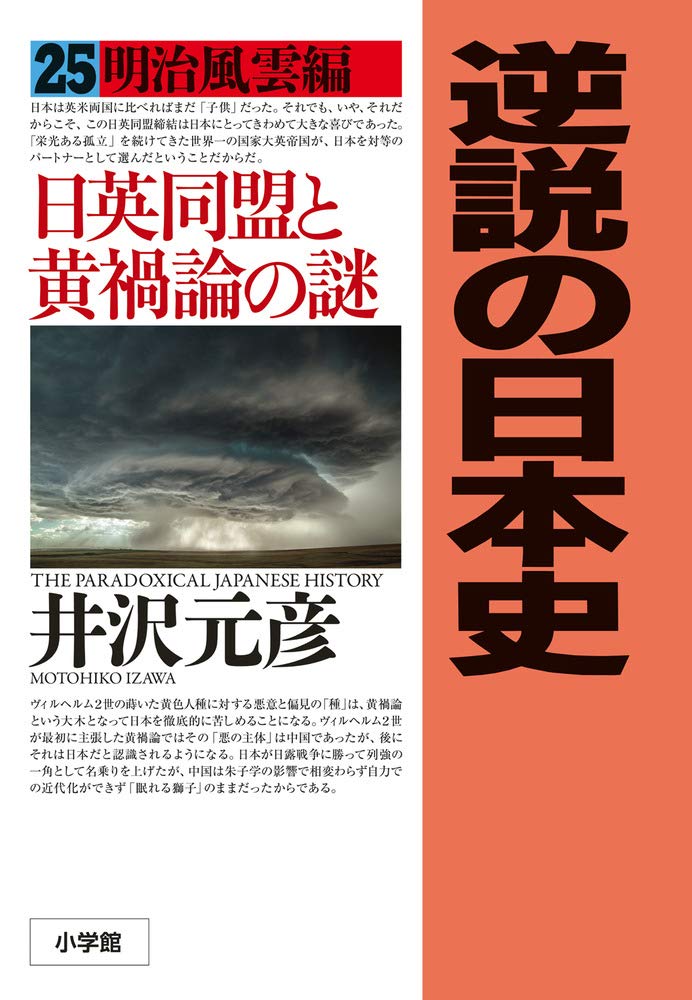光を当てる角度が違えば、真実の形も変わる
- 記事
前巻『逆説の日本史24 明治躍進編』の続編です。「躍進編」を読んだのは今から5年前、2020年の10月でした。当時すでに手元に25巻もあったのですが、少しずつ積読を消化して、この原稿を書いたのが2021年4月になっていたので、半年かけてようやくたどり着きました(積読とは、読む意思のある未読本の山のこと。つまり希望的観測の化石です)。
本巻では、幕末期の黒船来航から始まった攘夷思想が、欧米列強の圧倒的な軍事力を前にして転換を余儀なくされ、富国強兵・殖産興業へとシフトしていく――明治期のまさにクライマックスです。日露戦争を目前に、桂太郎首相らが京都・無鄰菴で「開戦やむなし」の決断を下す場面では、想像するだけで背筋が伸びます。国の命運を背負うというのは、私などの想像を絶するものなのでしょうが。
筆者の井沢元彦氏が一貫して主張しているのは、歴史分析で見落とされがちな「宗教的背景」の重要性です。時代ごとに形を変えながらも、日本人の根底にはケガレ忌避や怨霊、言霊といった宗教的感覚が連綿と受け継がれています。
私自身も無意識のうちに、こうした宗教的思想を判断基準にしている場面があります。たとえば「どう考えても論理的ではない判断を下したな」と後から振り返ると、そこに日本的な宗教観が潜んでいるのかもしれません。DNAレベルで刷り込まれているのだとすれば、恐るべし日本文化です。
物事を分析するとき、ひとつの視点からだけでは正しい全体像は見えません。会社の状態を把握する際に、損益計算書(PL)だけ見ても仕方がありません。貸借対照表(BS)とキャッシュフロー(CF)を併せて見るからこそ、はじめて会社の実態が見えてきます。
人に意見を求めるときも同じです。相手がどれほど優れた専門家でも、判断材料を漏れなく伝えなければ、的確な答えは返ってきません。逆に、自分が相談を受ける立場であっても、前提条件が不十分なままでは正しいアドバイスなどできるはずがないのです。たとえば「急ぎでこれをお願いします」と言われたとしても、その「これ」が何のためで、どんな成果をゴールとしているのかがわからなければ、仕事として完結しようがありません。経営の現場でもよくある光景です。だからこそ、あらゆる角度から質問を投げ、前提を整理し、漏れのない状態で判断を下す必要があります。
ここで、先ほど触れた言霊の話が関係してきます。あらゆる可能性の中には、当然ながら失敗リスクも含まれます。しかし、日本人の多くはこのリスク検討が苦手だと言われています。理由は、言霊思想――「口に出したことは現実になる」と信じる文化です。確かに、ポジティブな意味ではこの考え方は正しいです。強くイメージすれば、その通りに行動してしまうのが人間です。ですが、問題はそこから一歩踏み込まないこと。リスクを口にすることを避けるあまり、そうならないための対策やなってしまった場合の次善策まで考えないことがあります。これでは意思決定の精度が上がりません。
つまり、判断を誤らないためには、言霊を恐れずに失敗を言葉にする勇気も必要なのです。経営でも同じで、リスクを口に出してこそ対策が立てられます。沈黙は美徳ではなく、むしろ危険です。
歴史を読むということは、単なる暗記ではなくなぜそうなったのかを時代背景や宗教観から多面的に考察することだと思います。「愚者は経験に学び、賢者は歴史に学ぶ」とはよく言ったものです。歴史とは、無数の事例の中から多方向の可能性を考え抜く思考の筋トレです。幕末の尊王攘夷運動も、明治の富国強兵も、背景には当時の宗教観や社会構造が複雑に絡んでいました。そこに照らして読むと、歴史はただの年表ではなく、人間の意思決定学のように立体的に浮かび上がってきます。
歴史を学ぶことは、未来の判断を誤らないための最高のリスクマネジメントでもある――そう感じた一冊でした。