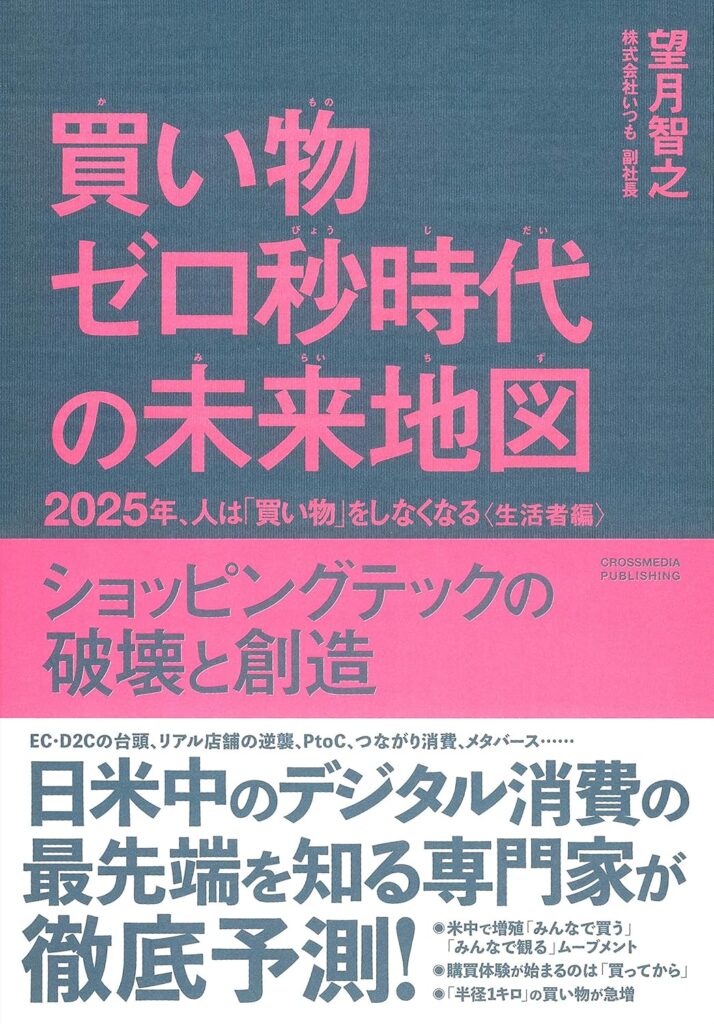デジタルが肥大させる経済格差
- 記事
2020年初頭、新型コロナウイルスが世界中に蔓延しました。多くの人の命を奪っただけでなく、世界経済にも大きな影響を与え、人々のライフスタイルを一変させました。私も例外ではなく、ライフスタイルが大きく変わりました。仕事のやり方が変わり、日常生活も一変しました。
仕事はほとんどテレワークになり、自宅で業務をこなすようになりました。業種や業界による差はあるものの、コロナ以前と比べると、多くの人の出社機会が減ったのではないでしょうか。
日常生活においても変化がありました。コロナ以前から、買い物はAmazonや楽天市場などのオンラインショップで完結することが多かったものの、外出が制限されていた期間中は、それらをより多用するようになったはずです。そして、その便利さに慣れてしまえば、外出できるようになった後も、わざわざリアル店舗に足を運ぶ理由はなくなります。
また、外食が制限されていた間も、UberEatsのようなデリバリーサービスを利用すれば、自宅で手軽に食事を楽しむことができました。こうして、日常生活において外出する必然性はますます減っていったのです。
ライフスタイルの変化に伴い、ビジネスのあり方も大きく変わるはずです。中には、大きな打撃を受けた企業もあったでしょう。この地球規模の変化の原因は、新型コロナウイルスの流行にあることは間違いありません。そして、すでに変わってしまったものを嘆いても仕方がない。問題は、これからどうすべきかです。
特に、ビジネスに打撃を受けた企業は、現状を詳細に分析し、新しいやり方に変えていく必要があります。私は、「生活が変化した」という認識は持っていません。確かに、今回のライフスタイルの変化は新型コロナウイルスがきっかけとなりました。しかし、オンラインで生活が完結する社会は、コロナがなくてもいずれ訪れる未来だったはずです。遅かれ早かれ、いずれはこのような変化が起こる運命にありました。つまり、コロナは単にその変化を前倒ししたに過ぎないのです。
オンラインサービスがこれほど発達していれば、生活スタイルの変化は、まったく新しい「黒船」ではありません。むしろ、当然の帰結として予想されていたものです。
人が生きている限り、買い物はなくなりません。例えば、ティッシュ、トイレットペーパー、シャンプー、ボディソープなどの日用品は、なくなる前に補充しておかなければなりません。しかし、補充が必要なことが分かり切っている生活必需品を、いちいち買いに行くのは手間です。
こうした課題を解決するため、越中富山の薬売りのように、なくなりそうなものを自動で補充してくれるサービスも登場し始めています。これにより、日用品の買い物に出かける必要性は、ますます減少するでしょう。
では、突発的な買い物はどうでしょうか。店に出かけて陳列棚を眺めながら「あれこれ検討する」ことは、もはや少数派になりつつあります。事前にスマホやタブレットで気になった商品のレビューを吟味し、十分に比較検討したうえで、「これだ」と思ったものをオンライン決済で購入する。翌日や翌々日には自宅に届く。もはや「買う」という行為にかける時間は、限りなくゼロに近づいているのです。
今すぐ商品が必要な場合はリアル店舗に行くこともありますが、その際も陳列棚を見て回ることは少なく、目的の売り場に直行することがほとんどでしょう。
リアル店舗が完全になくなることはないでしょう。しかし、必要最小限の数に集約され、役割も変わるはずです。従来のように「店頭で商品を見せて購買を促す」やり方は通用しなくなります。なぜなら、顧客はすでにオンライン上で無限の陳列棚を見ているからです。
その結果、リアル店舗の存在意義は、単なる商品陳列から**「顧客の購入意思決定をサポートする場」へと変わっていくでしょう。ユーザーの声というものは、コンシェルジュのような役割を持ち、「商品に関する詳しい情報」や「体験」**を提供する場としての価値が求められるようになるはずです。
今後、さらに新しい変化が起こるのか、それともこの流れが定着するのかは分かりません。しかし、今現在は、顧客が購買行動の前に行う「比較検討」の情報の質と量が、ビジネスの命運を握っていると言えます。
顧客にとって価値のある商品やサービスを提供できなければ、そのビジネスは破綻します。なぜなら、価値のないものには良いレビューがつかず、顧客が比較検討の際に「買うべき商品」として選択しなくなるからです。
逆に、価値あるものを作り出すことができれば、未来は明るいでしょう。これはオンラインビジネスに限らず、リアルビジネスでも同じことです。価値のないものは、リアルでもオンラインでも売れません。デジタル化が進むことで、その現象がより顕著に可視化されるようになっただけのことです。
すなわち、顧客にとって本当に必要なものだけが残っていく。これは、当たり前のことがより鮮明になっただけなのです。