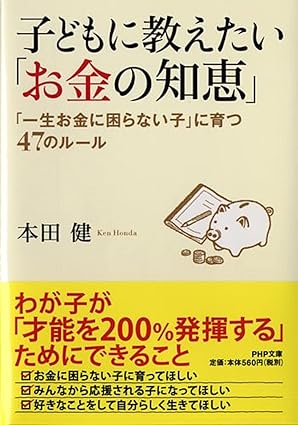お金は逃げない、逃げていくのは人
- 記事
子どもから大人まで、年代を問わず、お金についての知識は持っていた方が良いに決まっています。今あるお金に対する価値観は、間違いなくその人がこれまで歩んできた人生の集大成です。お金にどのように接してきたかが、その価値観のベースにあるということです。お金で不自由を感じたことがない人にとっては想像しにくいかもしれませんが、実際には、お金によって行動が制限される人がほとんどのはずです。私自身もそうですが、欲しいものややりたいことを、お金を理由に諦めた経験は一度や二度ではありません。
なぜ、お金によって不自由を感じるのか。本来、工夫次第で解決できることもあるはずです。今、読者の皆さんがお金で実現しようとしていることは、本当にそれでなければならないのでしょうか。代替案はないのか。少し落ち着いて考えてみれば、他の選択肢も見えてくるかもしれません。
とはいえ、物理的にお金の絶対量が足りないケースもありますし、他に代替案がない場合は、お金を集めるしか解決策はありません。では、どうやって集めるのか。お金は、お金のあるところに集まります。そして、お金は人が運んでくるものです。つまり、人が集まるところにお金も集まるということになります。したがって、まず人を集めることが重要です。
では、人が集まる場所とはどのような場所でしょうか。ざっくり言えば、周囲の人を元気にし、関わった人が幸せを感じられる場所ではないでしょうか。例えば、目先の私利私欲のために暴利をむさぼる会社があったとしましょう。そうした会社や業界が提供するサービスは、顧客満足度に欠ける傾向にあります。なぜなら、サービスの品質に対して顧客が支払う対価が釣り合っていないからです。そうした会社は、一時的に成功することがあったとしても、長期的には世の中から淘汰されていく運命にあります。なぜなら、その会社や業界のサービスを受けても幸せになれず、人が離れていくからです。そして、人が離れれば、お金も離れていくのです。
お金が集まらない会社の特徴は、考え方の順番が逆になっていることです。まずはじめに、サービス利用者が101%以上満足し、「またあそこでサービスを受けたい」と思えるような状況を作らなければなりません。100%では不十分です。100%というのは、顧客の想定通りのサービスであり、同等のサービスを競合他社が1円でも安く提供した場合に勝ち目がありません。逆に、顧客の想定を50%上回るような過剰なサービスを提供するのも現実的ではありません。なぜなら、長続きせず、提供者側が疲弊してしまうからです。
重要なのは、無理のない範囲で顧客の期待を1%でも上回り続けることです。それによって、リピート顧客が増え、紹介も生まれます。人が集まり、その結果としてお金も集まる。この順番こそが正解なのです。
ここで強調しておきたいのは、「顧客の期待を超えること」と「値引き」を混同してはいけないという点です。顧客が求めているのは、単なる価格の安さではなく、価格に見合った、あるいはそれ以上の満足感です。 値引きによって得られるのは、一時的な取引の成立に過ぎず、長期的な信頼関係にはつながりません。価格だけで選ばれるビジネスは、より安く提供できる競合が現れた瞬間に淘汰されてしまうからです。
ここで間違えてほしくないのは、値引きとは全く異なるという点です。特定の顧客の交渉によって値引きをすることは、値引きをしなかった他の顧客を裏切る行為であり、絶対に避けるべきことです。
また、顧客の声を聞かず、一方的に自社のサービスをPRすることは単なる自己満足に過ぎません。そのサービスに価値を見出すかどうかを決めるのは顧客です。顧客がサービスに求める価値(ニーズ)を掘り起こすことこそ、売り手の仕事ではないでしょうか。時折、自社の売り方を履き違え、自己満足に浸っている人を見かけますが、それは非常に残念なことです。
ぜひ、お金の習性を理解し、実践に活かしていただきたいと思います。繰り返しになりますが、人が集まらないところにお金は集まらないのです。